お疲れ様です、ichiです。
冬になると恋しくなる、こたつ。
あの何とも言えない“ぬくもり”と“安心感”は、他の暖房器具では代えがたいものです。
今回は、無垢の杉材を使った天板を再利用して、こたつを自作しました。

以前製作したこたつの天板を生かしつつ、下地から脚、ヒーター取り付けまでを一新。
サイズは1200mm×800mmと、2〜4人でも快適に使える大きめサイズです。
この記事では、
・杉無垢材の天板加工
・MDF下地の作り方
・ヒーター固定の構造
・脚の傾斜と取り付け方法
など、DIY初心者でも再現できるこたつ製作の全工程を詳しく紹介します。
YouTubeでも配信しているので、動画で観たい方はこちらをご覧ください。
杉無垢天板の再利用|反り止め金具を埋め込み加工

天板には、以前に製作した杉の無垢ボードを再利用しました。
サイズは、1200mm×800mm。
2人で使うにはゆったり、4人でも十分な広さです。
以前製作したものはこちら

杉材は軽くて加工しやすい反面、湿度変化による反りや割れが起こりやすい素材。
そのため、反り止め金具を裏面に埋め込み加工して、反りを防止しています。

埋め込み加工にすることで、見た目もスッキリし、テーブルとしての完成度も高まります。
埋め込み深さは金具厚より0.5mmほど深く掘ると、金具が出っ張らず仕上がりが美しい
下地づくり|厚さ12mmのMDF板を採用した理由

天板の下地には、ホームセンターでカットしてもらったMDF板(厚さ12mm)を使用。
サイズは、天板より少し小さめの「1100mm×700mm」にカットしてあります。
MDFを選んだのはヒータ部の断熱目的で、無垢材や合板に比べて反りにくく平滑性が高いため、ヒーターを取り付ける下地に最適。
このMDF板に、後述するヒーターや脚のプレートを直接取り付けていきます。

MDF板の上に天板を置くことになるので、すべり止めをつけておくと安心。
ヒーターの取り付け|角材で囲いをつくる工夫

ヒーターは、こたつの心臓部。
今回は、「36mm×21mm」の角材を使って、ヒーター囲い枠を作りました。
囲いは「相欠き継ぎ(あいかきつぎ)」で組み、強度と精度を確保。
ビスを使わないので、見た目の印象も良くなるメリットもあります。
組み上げた枠をMDF下地に固定し、その内側にヒーターを取り付けました。
囲いを作ることで、ヒーターがMDF板に直接触れず、放熱スペースを確保できます。
また、後々ヒーターを交換する際にも簡単に取り外せる構造です。
・相欠き継ぎは強度が高く、ズレにくい
・角材の角を面取りしておくと、安全で仕上がりも美しい
・ヒーターは電源コードの取り回しを想定して配置
ヒーターの取り付け手順

まずは、囲いとなる木材をカット。
内寸が290mmに必要だったので、400mmの長さにしました。

「相欠き継ぎ加工」をする箇所(内寸290mm)を、あらかじめ罫書きます。

深さ調整したスライド丸ノコで、罫書き線どおりに切り欠いていきます。
もちろん丸ノコでも、深さ調整することで出来ます。
今回は、36mm幅の材料を半分の「18mm」で切り欠き。

切り欠いた材料同士が、きちんと収まるか確認します。
入らなければ、再度調整します。

ノミで加工箇所を整えます。
削りすぎないように注意。

相欠き継ぎ加工で組んだ囲い枠に、ヒーターが入るか確認。

ヒーター本体に差し込む電源プラグの位置に、凹み加工をする必要があります。
ここはフリーハンドでカット。

ヒーター本体を固定するビスの穴をあけておきます。
設置面より12mm以上の高さで、200mm間の位置に2つ穴をあけます。

あけた穴から、ヒーターと囲い枠を固定します。

下地となるMDF板の中心に固定して、ヒーターの取り付け完了。
ボンドで囲い枠をMDF板に接着して、上面からビスで8箇所ほど固定しました。
傾斜脚の取り付け|快適な高さと安定性を両立
脚は、傾斜のついた木製脚(400mm)を使用。
こたつ布団と座布団を敷いた状態で、座ったときに最も快適な高さになるよう設計しました。
脚はプレートをMDF下地に取り付け、そのプレートにネジ式で脚を回し入れるタイプ。
これにより、シーズンオフには簡単に脚を取り外してテーブルとしても使用できます。
傾斜脚を選んだ理由は、単に見た目のデザイン性だけでなく、布団をかけたときのバランスが良くなるためです。
・MDFはネジの抜き差しに弱いため、金属プレート必須
・高さ調整は実際に座って確認するのがベスト
脚の取り付け手順

脚を取り付ける位置を対角線上にするので、対角線を引いておきます。
長いものがあると、端から端まで引けるので便利。

脚の土台となるプレートの固定位置を決めます。
今回は、角から「90mm」の位置にしました。

位置決めした位置に、ビスで4つのプレートをそれぞれ固定。

脚についたボルトで、プレート中心のナットに回し入れて固定。

脚を取り付けたらひっくり返して、グラつきなどの確認。
問題なければ、MDF板の端をサンドペーパーで面取りしておきます。
木の温もりを感じるデザインと仕上げ

杉材は軽くて柔らかく、触り心地も温かみがあります。
今回は再利用した天板のため、以前のオイル仕上げを活かし、軽く研磨して再塗装しました。
使用した塗料は、蜜蝋ワックス。
木目を引き立てつつ、こたつ特有の熱にも耐える塗装です。
・サンドペーパー#240〜#400で表面を整える
・ワックスは薄く伸ばし、乾燥後にウエスで磨くとツヤが出る
・熱や乾燥による割れ防止に、年1回メンテナンス塗装を
組み立ての流れ|DIY初心者でもできる工程

全体の製作工程をざっくりまとめると、以下の通りです。
- 杉無垢天板の反り止め加工(埋め込み金具取付)
- MDF下地のカット・面取り
- ヒーター囲いの角材カットと相欠き継ぎ組み
- 囲いの固定とヒーター取り付け
- プレート取付と脚のねじ込み
- 天板と下地の固定(または着脱式)
- 全体の高さ・バランス調整
- オイル塗装・仕上げ磨き
製作時間は、1日でもつくることが可能。
工具は、丸ノコ・トリマー・インパクトドライバーがあれば十分です。
コタツDIYの注意点|安全性とメンテナンス

自作こたつでは、安全面のチェックがとても大切です。
- ヒーターの熱が木材に直接当たらないようにする
- 通気性を確保して過熱防止
- 電源コードの取り回しに余裕を持たせる
- 長期間使用しない時はプラグを抜く
また、無垢材は乾燥により反りが生じることもあります。
季節の変わり目には、反り止めやビスの緩みを点検しておくと安心です。
実際に使ってみた感想|やっぱり“無垢”のぬくもり

完成後、さっそく使ってみました。
最初に感じたのは、天板の触り心地の良さと木の香り。
そして、杉特有の柔らかさが手に心地よく伝わってきます。
ヒーターの熱がじんわりと伝わり、まるで自然の中で暖を取っているような感覚。
無垢の木とMDFの組み合わせが、しっかりとした剛性と軽さを両立してくれています。
こたつに入るたび、「自分で作った」という満足感がふっと湧くのも、DIYならではの魅力です。
無垢材こたつのメリットとデメリット

メリット
- 木のぬくもりと香りが心地よい
- サイズや高さを自由に設計できる
- 自然素材ならではの経年変化を楽しめる
- 天板を再利用すればコストも抑えられる
デメリット
- 無垢材は湿度で反りやすい
- ヒーター取付位置に注意が必要
- MDFはネジの抜き差しに弱い
- 市販品よりも若干重くなる
それでも、自分の暮らしにぴったり合う一台を作れるのは、何ものにも代えがたい魅力です。
まとめ|“自分だけのぬくもり”を作るこたつDIY

今回のこたつDIYでは、杉無垢天板の再利用から脚取り付けまで、すべて手作業で仕上げました。
使い込むほどに味わいが増し、冬のリビングに欠かせない存在になりそうです。
DIYの良さは、単なる「モノづくり」ではなく、暮らしを自分の手で形にすること。
電気を入れた瞬間のぬくもりとともに、作る過程の記憶まで温かく感じられます。
YouTubeでは実際の製作動画も公開中。
「へいじつ木工」で検索して、ぜひ映像でもお楽しみください。
それでは皆さま、ご安全に。
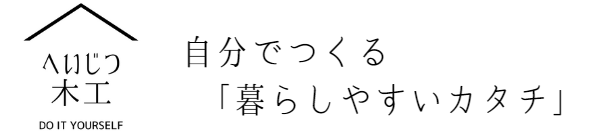





コメント